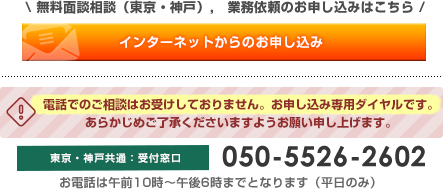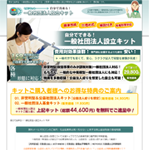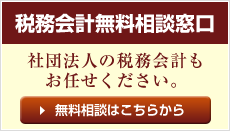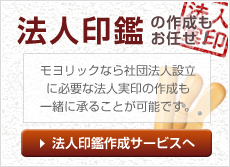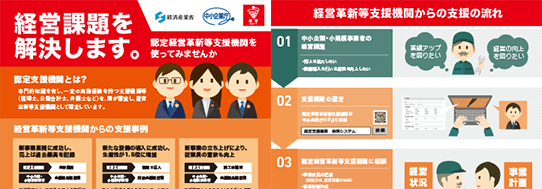一般財団法人設立の流れについて
手続きの概要
一般財団法人は、設立時に300万円の基本財産が必要になります。定款の作成後、当然に財産の拠出を行わなければなりません。
人的要件に関しては、一般社団法人は2名で設立ができる一方、一般財団法人は7名以上の設立メンバーが必要です。
一般財団法人の設立の流れを下記に掲載いたします。
流れを把握し、定款、機関設計等、法に則って確実に手続きを踏んでいく必要があります。
一般財団法人設立手続の流れ・フロー。全部で8ステップ。
- 1.定款を作成する。
- 2.公証役場で公証人の認証を受ける。
- 3.設立者が300万円以上の財産の拠出を行う。
- 4.定款の定めに従い、設立時の評議員・時理事・監事の選任を行う。
- 5.設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
- 6.法務局に設立の登記申請を行う。
- 7.登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する。
- 8.各役所へ法定の届出等を行う。
STEP1 定款を作成する。
設立者が一般財団法人の定款を作成します。設立者は一般財団法人へ財産を拠出する者であり1名以上で問題ありませんが、財産を拠出しない者は設立者にはなれません。法人も設立者になれますが、法人は理事、評議員、監事にはなれません。
設立者が法人の名称、所在地、事業目的、設立時理事、評議員、監事などの一般財団法人の基本事項を定款へ反映していきます。
設立者を除き、各役職(理事、評議員、監事)は兼任できませんので注意してください。理事3名、評議員3名、監事1名の合計最低7名が必要になります。
定款は法人を運営する上で大変重要なものです。特に将来、公益認定を見据えて設立するのであれば、単に一般財団法人が設立できれば良いというものではありません。必ず専門家へ相談しましょう。
STEP2 公証役場で公証人の認証を受ける。
定款が作成できたら公証役場で公証人の認証を受けます。
定款作成を専門家に依頼しない場合は、認証前に作成した定款原案を公証役場に持参して事前チェックしてもらいましょう。
公証役場に持参する他にFAXやメールでも対応してくれる公証役場もありますので、事前に電話で一般財団法人の定款認証を受けたい事を伝えましょう。
定款原案は公証人からの修正の指示があればそれに従って修正します。
最終的に問題がない定款ができたら、設立者全員が実印で押印します。認証日には、定款・設立者の印鑑証明書及び実印を持参します。
設立者全員が公証役場へ行けない場合は、代理人が代わりに認証を受けることもできます。代理人の場合、設立者から代理人への委任状が別途必要になります。
STEP3 設立者が300万円以上の財産の拠出を行う。
定款認証が無事終了したら、設立者は拠出金を振り込みます。まだ法人設立前ですので法人名義の銀行口座がありません。
ですので、設立者の個人口座へ振り込むことになります。設立者が複数名いる場合は代表者を一人決めて、その代表者個人の銀行口座へ拠出金をそれぞれ振り込みます。
代表者個人の銀行口座に拠出金の全額が振り込まれるようにしてください。
必ず設立者が自己の拠出金を全額振り込み、手数料を引いたりしないように注意してください。
設立者が一人の場合、本人の銀行口座に本人名義で振り込みます。
振り込みではなく預入でもいいと思われるかもしれませんが、これから設立する法人への拠出金だということを明確にするため振り込みで行いましょう。全ての振り込みが済んだら通帳のコピーを取ります。
STEP4 設立時の評議員・理事・監事の選任及び就任承諾
通常、設立時役員である評議員、理事(代表理事)、監事は定款で定めることができますので、定款附則に直接氏名を記載して選任します。設立時役員を定款で定めなかったときは財産の拠出後、定款の定めた方法で選任しなければなりません。
設立時代表理事は、設立時理事の中から選定することが義務付けられていますので注意してください。
設立時の役員を選任しても、その役員が就任を承諾しなければ効力は発生しません。
ですので、各役員から就任承諾を得てその書面(就任承諾書)を作成します。登記申請の際には、定款または設立時役員を選定した書面と就任承諾書が必要になります。
STEP5 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
選任された設立時理事、設立時監事は、選任後遅滞なく設立者から財産の拠出の履行が完了していること及び一般財団法人の設立の手続きが法令または定款に違反していないことを調査しなければなりません。
違反があったり不当な事項があった場合には、設立者にその旨を通知しなければなりません。
STEP6 法務局に設立の登記申請を行う。
一般財団法人の主たる事務所を管轄する法務局へ設立登記申請を行います。
設立時理事の調査が終わった日または設立者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に登記申請を行いましょう。代表理事が申請者となりますが、代理人が申請することもできます。代理人の場合は代表理事からの委任状が必要です。
法務局へ登記申請した日が法人の設立日です。設立日を希望する日にしたい場合は前もって法務局へ書類一式を持参して事前にチェックをしてもらったほうが確実です。
登記申請日に書類が足りない等、不備がないように余裕をもって準備しましょう。
STEP7 登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する。
法務局への登記申請から登記完了までは通常1週間程度掛かります。登記完了までに法務局から連絡がなければ無事に登記が完了しています。
登記完了後、法人の印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書が取得できます。
法人印鑑カードは代表理事が申請した法務局の窓口に法人実印と身分証明書を持参すれば、即日発行されます。
窓口に備えられている印鑑カード交付申請書に所定の事項を記載して窓口へ提出しましょう。合わせて、印鑑証明書、登記事項証明書も取得しましょう。
STEP8 各役所へ法定の届出等を行う。
無事法務局で登記が完了しましたら、役所へ法人の設立届を行います。
この設立届を提出する際に、登記事項証明書、印鑑証明書が必要になりますので、前もって役所の窓口へ必要書類を確認しておきましょう。
まずは税務署、都道府県税事務所、市役所へそれぞれ設立届を提出します。
必要に応じて、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署へ届を行います。特に税務署は提出期限内に提出しなければ、税務上のメリットが受けれない場合もありますので、設立後すみやかに行いましょう。
顧問税理士さんがついている場合は、顧問税理士さんが代行して行ってくれますので、相談してください。
顧問税理士がいらっしゃらない場合は、こちらのサイトから、公益法人の税務に精通した税理士・会計士を無料でご紹介させていただきます。お気軽にお問い合わせください。→公益法人税務ドットコム
【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。
「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。
知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。
無料面談相談のご予約はこちら
弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。
インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!
ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中
「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。
書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。
今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。
これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)
【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】