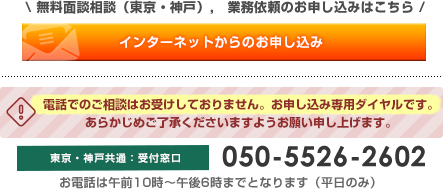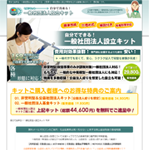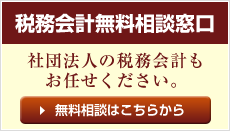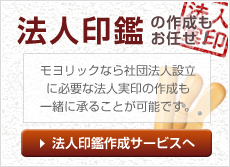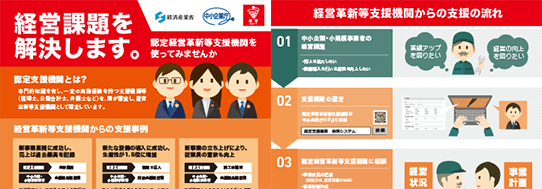一般社団法人とは?
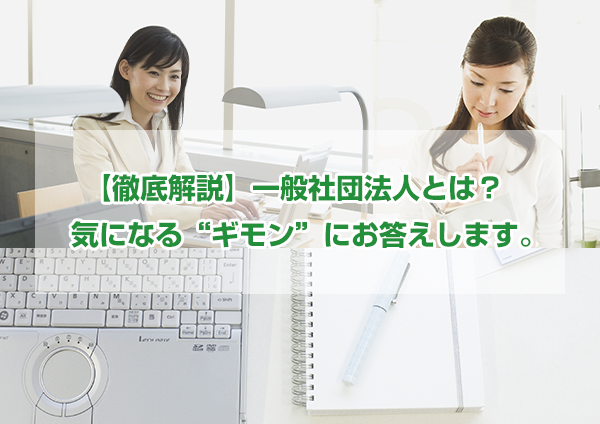
はじめまして。
当ページをご覧いただき誠にありがとうございます。
最寄りの頼れる専門家、行政書士法人MOYORIC(モヨリック)の津田と申します。
当ページでは、これから一般社団法人の設立をお考えの方に向けて、一般社団法人の特徴や、よくお寄せいただくご質問などについて、わかりやすく解説していきます。
当サイトは「行政書士法人MOYORIC(モヨリック)」が執筆、監修しています。
弊社は、平成18年の創業以来、延べ1,000社以上の法人様をサポートしており、現在、東京・神戸オフィスにて無料面談相談を実施中です。
一般社団法人の設立・運営に関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談くださいませ(無料面談相談のご予約はこちら)。
 行政書士
行政書士社労士
津田 拓也
この記事では、以下のポイントをわかりやすく具体的に解説していきます。
目次
それでは、見てまいりましょう。
最大のポイントは、営利を目的としない「非営利法人」であること

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律を根拠に設立される「非営利法人」を言います。
一般社団法人は、人(社員)が集まり、法律に規定されている手続きを踏むことによって成立します。
「人が集まることによって設立できる」と法律に規定されていますから、当然ですが、1名では設立することはできません。2名以上の人(社員)が必要になります。
株式会社や合同会社などの営利法人は1名以上で設立が可能ですので、そこがまず根本的に異なる点です。
一般社団法人の社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就くことが可能です。
一般社団法人の「社員」とは?
社員という言葉は、よく誤解をされがちなのですが、社会一般で言うところの「従業員」や「職員」ではありません。
従業員を1人も雇用していないので一般社団法人は設立できない。と勘違いをされている方もいらっしゃるのですが、そうではありません。
一般社団法人における社員とは、一般社団法人の重要事項を議決する最高意思決定機関の「社員総会」に出席し、その議決権を行使することができる人、または、法人等を指します。
一般社団法人においては、最重要人物と言っても過言ではありません。似て非なるものですが、株式会社における「株主」のような立場と考えてもらうと理解をしやすいかと思います。
*参考ページ:一般社団法人の「社員」について
非営利法人ってどういう意味?利益を上げてはいけないの?
一般社団法人は、必ずしも「公益的」な事業を行う必要はありません。
一般社団法人が行う事業の内容に制限はなく、株式会社や合同会社などの営利法人と同様に、基本的にはどのような事業も自由に行うことができます。
非営利という言葉は「ボランティア」や「公益事業」といったものを想起させますが、そうではありません。
一般社団法人は、「非営利性」さえ担保しておけば、「収益」を上げることのみを目的とすることも、法人内部の「共益」だけを目的とすることも可能です。
では、「非営利性」とは一体どのような意味なのでしょうか?
次は「非営利性」について、わかりやすく解説します。
「非営利」「非営利法人」とは?
“ 営利を目的としない = 非営利 ”とは、ボランティアや公益事業を指すわけではありません。
「非営利」という言葉には “ 利益を上げてはならない ” というニュアンスも含まれているように勘違いされがちですが、そうではないのです。
非営利とは、余剰利益を分配しないことを言います。
例えば、みなさまご存知の株式会社は、会社が儲かれば株主に余剰利益を配当することができますから「営利法人」になります。
一方「非営利法人」は、余剰利益が出ても、それを分配することはできません。
一般社団法人は「非営利法人」なので、余剰利益の分配はできないのです。
とはいえ、余剰利益の分配をしてはいけないだけですから、利益を上げること自体は可能ですし、もし余剰利益が出た場合でも、分配するのではなく、次の事業年度に繰り越して事業のために使えば良いだけです。
もちろん、一般社団法人の役員や従業員に役員報酬、給与を支給することも可能です。
ここでは簡単に、「利益分配ができない=非営利」と覚えておきましょう。
役所の許可は不要
一般社団法人の設立に、特別な「許可」や「認可」は必要ありません。
公証役場で定款の認証を受け、法務局で登記すれば設立が完了します(「準則主義」)。
この一連の流れは、株式会社や合同会社と同じです。
準則主義とは?
準則主義とは、該当する要件を満たしていれば、法人格が与えられる原則的な考え方をいいます。
法人設立に際して、行政機関の裁量が及ばず、要件を満たせば、設立登記によって法人格が与えられるのが特徴。
一般社団法人の活用例
一般社団法人は、比較的 “かんたん” に設立できる「非営利法人」として、さまざまな業界で活用されています。
一般社団法人という法人格を活用している業界の例
- 介護福祉、障害福祉事業
- 業界団体
- 職能団体
- 資格認定事業
- 協会ビジネス
- ソーシャルビジネス
- スポーツ振興
- 医療学会
- 学術団体
- 研究会
- 同窓会
- 自治会
上記のような事業で、一般社団法人は積極的に活用されており、年間約6,000法人が設立されています。
有名なところで言えば、自動車の自賠責保険を取り扱っている「一般社団法人日本損害保険協会」、トヨタ、本田技研、マツダなどが会員に名を連ねている「一般社団法人日本自動車工業会」、全国の金融機関が加盟している「一般社団法人全国銀行協会」などがあります。
その他、身近なところでは、確定申告など青色申告のサポートを行っている「青色申告会」も一般社団法人です(正式名称は「一般社団法人 全国青色申告会総連合」)。
全国各地の医師会、例えば世田谷区医師会、新宿区医師会、神戸市医師会なども一般社団法人で活動しています。
公益社団法人との違いは?
ここでは「一般社団法人」と「公益社団法人」の違いを解説します。
先ほどご説明したとおり、一般社団法人は「準則主義」なので、要件を整えて登記をすれば設立できます。
これに対し、公益社団法人の設立には、下記2段階の手続きが必要です。
公益社団法人の設立手続き
- 一般社団法人を設立する。
- 都道府県もしくは、内閣府に公益認定申請をおこない、認定を受ける。
このように2段階の手続きを経て「公益社団法人」が成立します(法務局に「名称変更登記」の申請を行わなければなりません)。
公益社団法人になれば、税制優遇を受けられるメリットがある反面、監督官庁の監督を受けることになり、一般社団法人と比較しても、より厳格な法人運営が求められます。
認定を受けた後も、認定基準を維持し続けなければなりません。
機動性の一般社団法人、優遇は多いが規制も多い公益社団法人。
活動目的や組織の規模など、総合的に判断しなければなりません。
公益社団法人については、下記のページでも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
*参考ページ:社団法人と一般社団法人の違いとは?
一般財団法人との違いは?
一般社団法人と似た法人に「一般財団法人」があります。
一般社団法人は「人」の集まりに重きを置いて活動するのに対し、一般財団法人は「財産」の集まりに重きを置きます。
一般社団法人は財産の拠出が “ゼロ円” でも設立は可能なの対し、一般財団法人は300万円以上の金銭若しくは財産の拠出を行うことが設立要件となっています。
人の集まりであるがゆえの「社団」、財産の集まりがゆえの「財団」と考えてもらったら分かりやすいかと思います。
一般財団法人については、下記のページでも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
*参考ページ:一般財団法人とは?
NPO法人との違いは?
次は一般社団法人と「NPO法人(特定非営利活動法人)」の違いをご説明します。
一般社団法人との一番大きな違いは、根拠となる法律です。
根拠法がそもそも違うので、一般社団法人とNPO法人とでは、その制度の成り立ちや、法律が作られた目的も異なります(非営利法人という括りでは同じですが)。
一般社団法人は、どのような活動でも行えるのが原則なのは前述のとおりです。
一方、NPO法人は「特定非営利活動促進法」で定められている「特定非営利活動」しか行うことができません。
設立手続きにおいても、両法人には大きな違いがあります。
NPO法人の設立期間は、一般社団法人よりも長くなります。
NPO法人の設立には、登記費用や定款認証手数料は一切掛かりません。
詳しくはこちらのページでも解説しておりますので、参考にしてください。
*参考ページ:NPO法人との違い
一般社団法人の組織・機関について

ここからは、一般社団法人の機関構成について見ていきましょう。
一般社団法人は「社員」で構成する「社員総会」のほか、「理事」を必ず置かなければなりません。
理事は1名以上いれば、問題ありません。
先ほど、社員は設立時に2名必要と説明しましたが、理事は1名でOK。
つまり、延べ人数2名で一般社団法人は設立できるということになります。
理事と社員は兼任できるからです。
このほか、定款の定めによって、それぞれ「理事会」「監事」「会計監査人」を置くことができます。
これらの機関を置くか否かは法人の判断に任せられています。
理事会を置く場合は、理事3名以上、監事1名以上の人員を満たす必要があります。
なお、法に規定されている一般社団法人の機関設計は、以下の5パターンとなります。
一般社団法人の期間設計5パターン
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
1. から順に【小規模 → 大規模】になっていくイメージでご覧いただければ分かりやすいかと思います。
- 社員総会とは?
- 「社員」によって、法人の重要事項を決定する機関
「社員総会」について更に詳しく - 理事とは?
- 法人の代表機関であって対内的に法人の事務を執行し、対外的にはその法人を代表する
「理事」について更に詳しく
一般社団法人の基金制度について
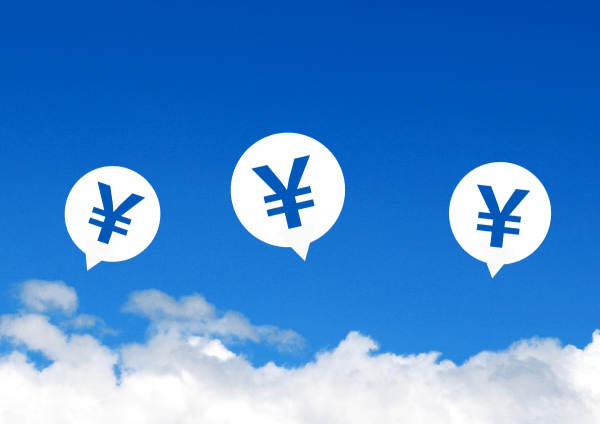
この基金制度は、一般社団法人だけに認められたの制度です(一般財団法人などには基金制度は存在しません)。
一般社団法人の基金制度は、株式会社の資本金と性質が異なります。
基金制度のポイントは下記の3つです。
基金制度のポイント3つ
- 登記事項ではない
- 一定の条件のもとに返還義務がある
- 定款に記載する必要がある
基金制度の詳細は下記のページで詳しく解説しています。
*参考ページ:一般社団法人の基金について
一般社団法人の「税制」について -2つの形態があります-

一般社団法人は、税制上「普通型」と「非営利型」の2種類に分かれます。
普通型は、株式会社や合同会社などの普通法人と同等の課税形態となります。
これに対し、非営利型は、税制上の優遇措置が設けれています。
非営利法人の代表格とされる「NPO法人」とほぼ同等の税制優遇措置を受けることができるのです。
NPO法人の場合は、設立するのに管轄官庁の認証が必要であるのに対し、非営利型の一般社団法人は、一定の要件を備えた上で登記さえすれば、設立が可能です。
これらの理由から、現在は、NPO法人よりもこの非営利型一般社団法人が多く活用されています。
詳細はこちらをご覧ください。
*参考ページ:一般社団法人の税制と非営利型の要件について
一般社団法人のよくある勘違い

ここでは、一般社団法人について誤解されがちな項目について、正しい知識と共に、わかりやすく解説します。
ご自身の知り得た情報に勘違いがないか(お間違えがないか)、照らし合わせながら、ぜひご確認ください。
1.利益を出してはいけない。
前述の通り、非営利と聞くとボランティアや無償活動のようなイメージを持つ方が多いのですが、利益をあげてはいけないという意味ではありません。
利益をあげてもまったく問題なく、その利益を社員に分配してはいけないだけです。
2.役員報酬や賞与を出すことができない。
一般社団法人の理事や監事は、法人と「委任契約」によりその業務を行います。
ですので、その職務執行の対価として役員報酬や賞与を出すことができます。
報酬を支払うことは当然のことなのです。
3.従業員を雇えない。給与をもらえない。
ボランティア的なイメージが強いのか、従業員を雇えない(ボランティア)と思っている人が見受けられますが、一般社団法人でも従業員を雇うことができます。
また、従業員は労働の対価として、給与を受け取ることもできます。
4.公益性がある事業でないといけない。
“非営利法人=公益性” だと思われている面がありますが、一般社団法人の行う事業に制約はありません。
もちろん公益性がある事業も行えますが、公益性がなくても問題ありません。
5.設立したら監督官庁から監督される。
一般社団法人には、監督官庁が存在しません。
設立に際し、行政の許可等は不要で、設立後も行政から監督、指導を受けることはありません。
一般社団法人の「特徴」のまとめ

これまでご説明した一般社団法人の特徴をまとめておきましょう。
- 法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)
- 社員2名以上で設立ができる
- 理事は1名以上いれば足りる
- 設立時に有する資金・財産がなくても設立が可能
- 社員、社員総会及び理事は必置
- 理事会、監事、会計監査人を置くことができる
- 基金制度を設けることができる(定款での定めが必要)
- 原則課税(普通型一般社団法人)と原則非課税(非営利型一般社団法人)の2種類の法人形態がある
一般社団法人に関するQ&A

ここまでは一般社団法人の特徴について、知っておいていただきたい知識をお伝えしてきました。
続いては、弊社がお客さまからよくお寄せいただく “ 一般社団法人に関するご質問 ” をピックアップして、一問一答形式でお答えしていきます。
ここでは下記15の質問にお答えします。
一般社団法人に関するQ&A
これから一般社団法人の設立をお考えであれば、参考になるQ&Aかと思いますので、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
一般社団法人の設立するための条件は?
社員は最低2人、理事を1人以上置く必要があります。
社員と理事は兼任できますので、法人のメンバーとして最低2人以上いれば資本金0円でスタートできます。
資本金もなく、2人から設立できますので、難しい条件はほとんどありません。
社員には資格の制限等はなく誰でも就任できますので、夫婦で設立も可能です。
その他、身近なところですと、親子、友人同士での設立も考えられます。
一般社団法人は行う事業内容も制限はありませんから、株式会社などの営利企業と同様、公序良俗・法令に違反しない限りはどんな事業でも行うことが可能です。
一般社団法人の名称、事業目的、所在地等を決めて社員で定款を作成し、公証役場で認証を受けた後に管轄の法務局へ設立登記の申請を行うことで設立は完了します。
一般社団法人を設立するにはいくら掛かりますか?
法定実費として、定款認証手数料が約5万円、登録免許税が6万円かかりますので、計11万円です。
その他、私共のような専門家に設立手続きの代行をご依頼される場合は別途報酬が必要になります。
法務局での設立登記申請には法人実印も必要となりますので、その作成代金も見ておきましょう。
法人実印の費用はショップによって異なりますが、5千円から~2万円が相場です。
弊所でも法人実印の販売をしておりますので、ご入用の際はお気軽にお申込みください。
品質重視で最短即日での発送も可能です。
行政書士法人MOYORICの法人実印作成サービス
一般社団法人の設立手続きは素人の私でもできますか?
はい、できます。行政書士や司法書士などの専門家に頼まなければ設立はできないと思っていらっしゃる方もいますが、そうではありません。
ただ、公証役場や法務局に何度か足を運ぶ時間と根気が必要になります(公証役場での定款認証と管轄の法務局での設立登記申請の2つの手続きが必要です)。
ご自身でも一般社団法人法をしっかり勉強される根気と時間がたっぷりあるのであれば、設立は十分に可能かと思います。
まずは、当サイトで手続きの流れや必要書類、設立のための要件などの事前知識を仕入れてください。
当サイトを熟読いただければ、手続きの全容は十分に掴んで頂けると思います。
その後、実際の書類作成に移ります。
必要書類の作成の難易度については、設立する法人の内容によって大きく異なります。
少人数で普通型法人を設立するのか、中規模の人数で理事会を設置して非営利型法人にするのか、あるいは公益法人成りを目指して大規模型の法人にするのか。これらの別によって、必要書類の数、中身は大きく異なります。
いずれにしても、ご自身で設立は可能ですが、決して難易度は低くない(設立後も円滑に運営ができるかどうかも含め)とお考えください。
そのくらいの心つもりで設立手続きにあたれば、設立手続きはもとより設立後の運営も円滑に運ぶことができるしょう。
なお、当サイトでは、下記書式集も販売しております。
ご自身で設立手続きを行って頂くためのDIY書式です。
自分で出来る!一般社団法人設立キット
※あらゆる法人形態に対応しておりますので、安心してご利用いただけます。
一般社団法人は従業員を雇えますか?
もちろん一般社団法人でも従業員を雇用できます。
雇用後は株式会社等と同様に従業員の社会保険や労働保険の加入等、雇用後の手続きが必要です。
一般社団法人法上の「社員」を従業員として雇用することも特には差し支えありません。
一般社団法人の役員報酬はどのように決めるのですか?
役員報酬は定款への記載、または、社員総会の決議で決定します。
一般社団法人の役員(理事や監事)の報酬は、定款で直接定めることもできますが、社員総会の決議で決めることが一般的です。
役員報酬の総額だけを社員総会で定めて、各役員に支払う具体的な報酬額については、理事会設置法人であれば理事会の決議において決めることになります。
一般社団法人の事業目的に制限はありますか?
一般社団法人が行う事業目的に制限はありません。
公益事業に限定されることもありませんので、収益事業を行うことも可能です。
ただし、利益を分配すること=社員に剰余金や残余財産の分配を行うことはできません。
なお、一般財団法人を設立後に公益認定を受けて、公益法人を目指す場合には公益目的事業に該当する事業を行う必要がありますので注意してください。
一般社団法人は税金の優遇がありますか?
一般社団法人は、株式会社等と同様に通常、全ての所得が課税対象になります。
しかしながら、一般社団法人の中でも「非営利型法人」の要件を満たせば、会費や寄付金・基金による所得は非課税対象となり、収益事業による所得のみが課税対象となります。
「非営利型法人」の要件を満たすことにより、税法上の優遇を受けることができます。
非営利型法人の要件は?
「非営利型法人」は、利益が出た場合に剰余金の分配を行わないことはもちろん、解散した場合でも手元に残った財産は国や地方公共団体等へ寄付することなどをあらかじめ定款に定めなければなりません。
また、理事の人数は3人以上置く必要があり、理事と親族である理事の人数は理事総数の3分の1以下であることも条件です。
会員の会費によって事業を行う「共益的活動を目的とする法人」では、上記の他、会員に共通する利益を図る事業を行うことを目的とし、主たる事業として収益事業を行わないこと、定款に会費の定めがあること等が必要です。
非営利法人とはなんですか?
営利を目的としない法人を「非営利法人」といいます。
非営利とは「利益の配当をしない」ことです。
例えば株式会社であれば利益が出ると株主に利益を配当しますが、非営利法人は利益(剰余金)が出ても社員に配当を行うことや残余財産の分配を行うことができません。
つまり、法人がいくら儲かっても配当がなく、法人が儲けるというような概念がありません。
ただし、配当をしなければいいだけですので、収益事業を行って得た利益を法人の活動費用や役員報酬等に充てることは何ら差し支えなく、基本的には自由に事業を行うことができます。
どのような事業内容が一般社団法人に向いていますか?
共通の目的のために集まって活動する団体に向いています。
非営利法人ですので儲けが主体ではなく、例えば任意団体を組織化したい場合や会員制の組織(協会、学会、同窓会)などを法人化する場合に向いている法人です。
もしこのような集まりが営利を目的としたいのであれば、株式会社や合同会社になります。
例えばボランテイア活動をしている団体を法人化したい、同好会やサークル活動などを法人化したい、学会や研究団体を法人化したい場合などに向いていると言えます。
資本金がなくても設立できますか?
一般社団法人には、資本金は要りません。
ですので、手元資金が少ない場合でも設立が可能です。
設立直後は法人には収入がありませんので、法人の活動を行うにあたって必要な経費は社員が負担します。
しかしながら、一般社団法人を運営していくためには、一定の資金が必要になります。
このため任意ですが、資金調達の手段として「基金制度」を設けることができます。
※参考ページ:一般社団法人の経費は誰が支払う?
株式会社が社員となれますか?
一般社団法人の社員の資格は問われませんので、個人はもちろん株式会社などの法人でも社員になれます。
設立時社員の人数は2名以上必要となりますので、1名が法人、1名が個人であっても問題はありません。
ただし、法人は一般社団法人の役員(理事・監事)にはなれませんのでご注意ください。
尚、社員の資格は法人の定款の定めるところにより、「社員の資格の得喪に関する規定」を設けることができます。
一般社団法人の社員に「資格」について詳しく教えてください。
一般社団法人は2名以上の人(社員)が集まって設立します。
設立時の社員は最低2名ですが、法人設立後に入社する社員についての資格を定款で定めることができます。
一般社団法人の「社員」は法人の重要事項を決定する社員総会において議決権を行使することができます。
社員総会は、毎年事業年度終了後に行われる「定時社員総会」や役員を選任する際などに行われる「臨時社員総会」があり、この社員総会において、決算書の承認をしたり、新しく役員を選任したりします。
社員は法人のオーナー的な立場にあたり、法人にとって大変重要な役割を担っていますので、社員になるための加入資格を定款で設けることができるのです。
例えば、単に「代表理事の承認を得ること」と規定することもできますが、より詳細に「○○業を営む者であること」や同窓会など共益的活動を目的とする法人では、「○○大学の卒業生であること」と規定することもできます。
また、加入条件の他にも退任する場合の手続きや社員の資格を失う場合などについても定めることができます。
社員と理事の違いって?
一般社団法人の「社員」と「理事」の違いがよくわからない人もいると思います。
簡単にいうと社員は「法人のオーナー」、理事は「法人を運営する人」です。
理事は、社員総会で社員によって選任されます。
社員総会以外で理事が選ばれることはありません。
つまり、理事を選ぶ権利を持っているのは法人のオーナーである社員だけであり、社員の方が理事より立場が上だという事になります。
社員=理事という事はよくありますが、立場上はまったく別人格です。
理事は、一般社団法人から委任を受けて法人の運営を任された人です。
理事は1名以上必要ですが理事会を設置する場合は、理事3名以上と監事1名以上が必要です。
法人の実情に応じて定款で理事や代表理事の人数を定めることもできます。
社員・理事に任期はありますか?
社員に任期はありませんが、理事には任期があります。
理事の任期は原則2年(※)ですので、最低2年に1度は再度理事を選び直す必要があります。
任期が経過すると自動的に退任している事になりますので、同じ人が続投する場合でも法務局へ理事の変更登記の申請を行う必要があります。
逆に社員には任期はありませんし、名前が登記されることもありませんので、社員に変更(入退社)があった場合でも法務局へ登記申請をする必要はありません。
社員の変更(入退社)は定款の規定に基づいた法人内部の手続きになります。
※理事の任期は、正確には選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会が終結する時までです。
【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。
「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。
知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編)
*ワンクリックでいつでも解除できます。
無料面談相談のご予約はこちら
弊社では「お客様それぞれのニーズ」に合わせた一般社団法人の設立に関するご相談を承っております。
東京・神戸オフィスにて無料面談相談も実施しておりますので「専門家の話をじっくりと聞いてみたい」という方は、お気軽にご利用下さい。
インターネットでのお申し込みはこちら
【24時間受け付けております】

設立をお急ぎの方も、ぜひ一度ご相談くださいませ。
一般社団法人・NPO法人 設立実績 100 法人以上!相談件数 300 件以上!非営利法人専門。迅速・丁寧なサービスが自慢です!
ご購入者様 800 名突破!
「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中
「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」
とお考えの方は、詳細マニュアル付きの穴埋め式書式集(キット)をお勧めいたします。
一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。
書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。
あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。
今なら、一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中(一般社団法人設立キットのみの特典です)。
これまで一般の方 800 名以上(2023年12月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス)
【社団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般社団法人設立キット【29,800円】
【財団設立キットはこちら】
自分で出来る!一般財団法人設立キット【29,800円】